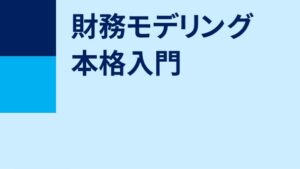事業計画・業績予想は結論ありきか? 財務モデリングのアートの要素【質問箱】
【質問】価値算定の結果は、根拠のない仮定に大きく依存するのではないか
第三講 予想損益計算書|売上高の予想方法 | 財務モデリング本格入門 に関するご質問をいただきました。
価値算定の結果は、業績予想の仮定(いわゆるエイヤーで決める部分)にかなり依存しませんか? 結局、結論が先にあって、そこに数字を合わせてこじつけている感じがしており、財務モデリングを行うことに何のメリットがあるのか分かりません。
"Querie" - 一部修正
なお、財務モデルは、業績予想を株式価値に変換するツールです。業績予想をするためのツールではありません。詳しくは 第一講 財務モデリングとは? | 財務モデリング本格入門 をご覧ください。
【回答】結論ありきで事業計画を作るのは難しい
確かに、価値算定の結果は、業績予想(事業計画)に大きく左右されます。
それにもかかわらず、実務において問題になっていない理由をご説明します。
誰が事業計画を作成し、誰が財務モデリングを行うのか
事業計画を作成する人と、株式価値を算定する人が同一人物だったら、結論ありきで事業計画が作られることもあるでしょう。
しかし、実務上は、事業計画を作成する人と、株式価値を算定する人は、異なることが多いです。
企業買収・事業投資の案件においては、評価される側(被買収企業の経営陣など)が事業計画を作成し、評価する側(買い手企業の経営企画部門など)が財務モデリングを実施します。
したがって、業績を予想する人と、財務モデルを作る人では、利害が一致していません。
結論ありきの事業計画を作るとどうなるか
確かに、評価される側が、自分でも財務モデルを作成して、「株式価値が100億円となるような事業計画」を逆算して作成することはあるでしょう。
しかしながら、これをやってしまうと、評価する側から質問攻めにあいます。
- 売上が成長する根拠は?
- 利益率が改善する根拠は? 改善した実績は?
- 単価を確認したいから、顧客との契約書を見せてくれ
- 増産の実現性を確認したいから、工場を見せてくれ
そして、結論ありきで業績予想を作成してしまうと、上記のような質問に答えられなくなり、評価する側から、「信用できないので投資はしない」と言われてしまいます。
事業計画の最終的な目的
企業買収の文脈において、対象会社側の最終目標は、自社を高く売ることです。ベンチャー企業が資金調達をする場合でも同じです。高い評価額で株式を引受けてもらうのが目的です。
確かに、強気な事業計画を作成することは、高く売る・高く評価してもらうためには必要なことです。
ただ、それが過度なレベルになってしまうと、買い手企業からの信用を失い、そもそも買収・出資をしないという結論になってしまうでしょう。
したがって、評価される側が作成する事業計画は、ある程度は盛られていますが、せいぜい3-5割程度しか盛られていないことが多いです。(それ以上に盛った場合、そもそも破談になる可能性が高いでしょう。)
価値算定・事業計画のアートの要素
前のセクションに書いたように、結論ありきで事業計画を作るのは容易ではありません。
一方で、結論ありきな部分が全くないのか?というと、ある程度はあります。特に根拠なく適当に設定された数値に、株式価値が大きく左右されることもあります。
このような性質があるため、事業計画はエイヤーで作成するとか、価値算定にはアートの要素があると言われます。具体的に考えていきましょう。
客観的なデータに基づく事業計画の修正
前述のとおり、評価される側が作成した事業計画は、ある程度盛られています。評価する側は、自前での調査や、質疑応答などを通じて、盛られている部分を修正していくことになります。
客観的なデータをもとに修正できる場合は、そのように対応します。例えば、次のような修正です。
- 被買収会社は、事業Aの売上高が毎年10%成長すると言っている
- しかし、過去実績としては5%しか成長していない
- 市場の長期的な成長率も5%程度であり、将来加速する根拠は特にない
- 有力な競合が撤退した等の特別な事情もない
- よって、10% → 5% に修正する
特に根拠のない仮定/いわゆるアートの要素
データを得られた部分については、データに基づいて修正するのですが、実際には、データも根拠も何もない部分もたくさんあります。
こういう部分では、特に根拠のない修正が発生します。「エイヤーで決める」とか「アートの要素」と呼ばれる部分です。
- 被買収企業は、事業Bが5年で2倍に成長するといっている
- ヒアリングの結果、5年で2倍はさすがに盛られていると思われる
- しかし、5年で何倍が妥当かはよく分からなかった
- よし、5年で1.5倍にしよう
上記の場面において、5年で1.5倍か、1.2倍か、1.8倍かは、特に根拠なく決めることになります。
このような修正を行った場合、価値算定の結果が、特に根拠のない仮定に左右されることになります。そして、このような修正を行う箇所は、ゼロにはなりません。どこかでは行います。
このため、価値算定にはアートの要素があると言われます。アートとは、ロジックでないものくらいの意味合いです。
価値算定・意思決定における社内での分業
以上は、事業計画の作成者と、価値算定の実施者が異なる前提で説明しました。
しかしながら、実際にはどちらとも社内で行われているというケースもあるでしょう。この場合でも、厳密にみると、評価する側と評価される側が異なることが多いです。
以下のように、結論ありきの事業計画にならないようにするためには、評価する人と評価される人が独立していることが重要です。
もっとも、コーポレート・ガバナンスの体制が整っている企業であれば、通常は以下のような分業・意思決定になっていると思います。
事業部門とコーポレート部門の分業
事業部門が事業計画を作成し、コーポレート部門が価値算定を行うなど、部署間で分業しているパターンがあります。
この場合、事業部門が作成した事業計画はある程度盛られていることが多く、コーポレート部門のほうが現実的な目線を持っていることが多いです。
もちろん、コーポレート部門の見立てが悲観的すぎて、むしろ事業部門のほうが現実的であるというパターンもあります。
取締役会や投資委員会による判断
取締役会や投資委員会が設置されているケースもあります。担当部門が事業計画を作成し、価値算定を行うが、その妥当性は投資委員会が判断する、といった構造です。
この場合、取締役会/投資委員会のメンバーが、案件メンバーを兼務することは好ましくありません。
メンバーに兼任があると、評価する側とされる側が一致してしまい、結論ありきの価値算定になるリスクがあるからです。
企業金融の学習では、立場を想像するとよい
企業金融の領域では、誰が実施するのか、誰の立場でそういう理論になっているのか、を考えながら学習するのがおすすめです。
企業金融の仕事、特に企業買収の仕事では、非常に多くの利害関係者がいます。1つの買収プロジェクトで、100人も200人も関係者がいるのですから、当然、全員の利害は一致しません。
学習の際には、各理論や各主張が、誰の立場から行われているものかを考えるとよいでしょう。
「企業価値は高いほうが良い」というのは、売り手にとっては正しいかもしれませんが、買い手にとっては正しくないかもしれません。